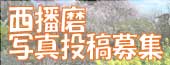野部縁切り地蔵尊なんてのがある【たつの市神岡町野部】
たつの市神岡町野部に野部縁切り地蔵尊があった。こちら↓

通りから入った静かなところに、ひっそりとありました。

靴を脱いで上がるようになっていて、壁には、男女の縁切などが書かれた紙や封書が画鋲でとめられています。

県道724号線沿いに「野部縁切り地蔵尊」の看板が上がっています。
看板には、
縁結びの神様やお地蔵さんは各地にあるが、男女の悪縁や競馬などの賭け事、酒などの縁を切るというお地蔵さんは、珍しいと言える。
縁切り地蔵の由来は、元禄年間(1688~1704)、鳥取藩の若侍が町人の娘と恋仲になった。階級制度の厳しい封建時代にはかなわぬ恋であった。娘との絆を断ち切るために、江戸勤番を願い出て藩主のお供として、鳥取を出発した。娘は男恋しさから行列の後を追った。美作街道の千本宿(たつの市新宮町)に着いた時に、若侍は同僚から注意され、娘に「鳥取に帰るよう」と諭したが、娘は聞き入れず、五月二十四日も行列を追った。市野保(たつの市神岡町) まで来たとき、同僚が笑うので後を振り返ると、娘が若侍を追って来たため逆上し、娘を切り殺した。
若侍は自分の行為を慚愧(ざんき)し、延べで松の木の下で切腹して果てた。 通りかかった野部の村人に、「亡魂ここに留まり、私のような悪縁に悩む人々を救う」と遺言した。村人は若侍の死を哀れみ五輪塔を建立して、毎年五月二十四日の命日に供養をしてきた。若侍の遺言通り「悪縁を切る」の霊験あら高さに、村人は明治初年、地蔵を勧請(かんじょう)して祀ってきた。
縁切りの願いをかける方法は、男女の悪縁の場合、相手の履物の緒を切って供えるか、持ち物を壊して供える。麻雀でははいを壊して供え、酒の場合は杯を割って供えると、効果があると言い伝えている。 龍野史談会
地図でいうとココ↓
より大きな地図で はりまっぷ「播磨まちネタまっぷ」 を表示
こちらの記事もオススメです
タグ
2012年8月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:まちネタ




 兵庫県立龍野実業高等学校が閉校している。【たつの市龍野町北龍野】
兵庫県立龍野実業高等学校が閉校している。【たつの市龍野町北龍野】 ~みんなでまちづくり「Sou-Zou(ソウゾウ)」事業~ 「自立のまちづくりアイデア」を募集している【たつの市】
~みんなでまちづくり「Sou-Zou(ソウゾウ)」事業~ 「自立のまちづくりアイデア」を募集している【たつの市】 龍野旧市街を中心としたイベント情報チラシがある【たつの市龍野町】
龍野旧市街を中心としたイベント情報チラシがある【たつの市龍野町】